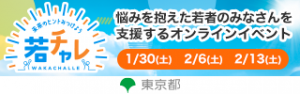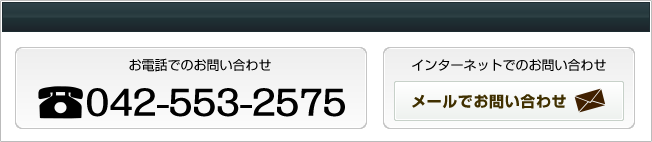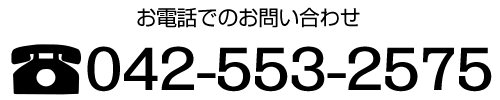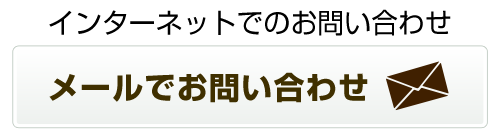当法人が、毎月 1 回開催しております施設見学会、午前中に支援諸機関向け説明会、午後に当事者・家族等個人向け説明会と 2 回に分けて実施しております。
これによって、支援諸機関の方々にとっては、当事者支援の方法をより具体的にご理解いただけ ます。
ご参加いただいた自治体等の担当者の方は、ひきこもり支援の窓口を準備しているなど、効果的な支援のヒントになったと高評価をいただいております。
また、当事者・家族の方々にとっては、生活上の具体的な対応方法等の質問にもお応えいたします。
特にご家族の方々は、前もって感じていた不安が、思っていたより明るい雰囲気だった、説明もわかりやすかった、と少しだけでも安心していただけたのがよかったと思います。
今、ひきこもっていても、(誰かの手助けが)一歩外へ出るための適切な機会となり、信頼できるプログラムによって、社会の中で自分らしい人生を送ることができる若者がいる。
私たちは、機会と信頼によって、そんな若者の希望を一緒に実現したいと思っています。
ニート・ひきこもり状態の若者のご家族の方、支援に関わっている方、ご関心のある方は是非ご参加ください。お待ちしております。
・実施月日:2021年3月10日(水)活動説明・施設内見学
※2021 年 4 月開講の宿泊型集中訓練プログラムの詳細を説明させていただきます。
①関係諸機関向け見学会 10:00~12:00
②当事者・家族等個人向け見学会 13:30~15:30
2021年4月14 日(水)時間帯は上記と同じです。
参加者アンケートから
〇禁止事項が思ったより少なく自由な風土に感じました。「合宿」「寮」というwardがどうしても自由度が低いイメージなので、私がかかわっている相談者に伝える際は、その点をしっかりお伝えしようと思いました。
〇きめ細かく対応されている様子が分かりました。説明がゆっくり丁寧で質問への応答も的確で利用者の方にどのように接していられるかが想像できました。
〇アウトリーチについて、時間をかけた本人との信頼関係を構築することをとても大切にしていらっしゃることが印象に残りました。
お申し込みは、電話でご予約をお願いいたします。
電話 042-553-2575(平日・土・日共) 9:00~16:00受け付けています。

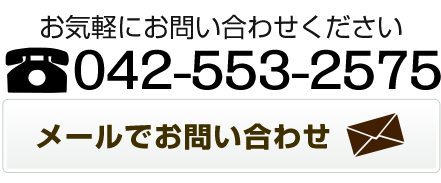



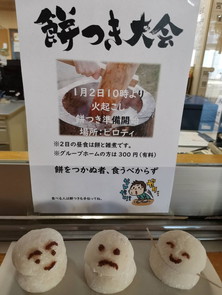
 最初の工程として、蕎麦粉と小麦粉を混ぜ合わせた物に少しずつ水を回し、一塊にして捏ねていく作業をしていきます。使用している道具や、粉の割合は同じにも関わらず、水っぽく粘り気がある物や、反対にマットな質感でひび割れが見える物等、違いは一目瞭然。
最初の工程として、蕎麦粉と小麦粉を混ぜ合わせた物に少しずつ水を回し、一塊にして捏ねていく作業をしていきます。使用している道具や、粉の割合は同じにも関わらず、水っぽく粘り気がある物や、反対にマットな質感でひび割れが見える物等、違いは一目瞭然。
 切る際にイメージする麺の形状にならないのです。写真の様に、きしめんに近い物や、極端に短い物になってしまう事が多く、悔しさを滲ませながらも、茹でる前段階まで漕ぎつけた事で、一定の達成感を得られた様でした。その後、麺を茹でて無事に完成し食べてみると、一纏めにして捏ねる作業が、如何に蕎麦としてのクオリティを左右するものであるかを実感したのでした。
切る際にイメージする麺の形状にならないのです。写真の様に、きしめんに近い物や、極端に短い物になってしまう事が多く、悔しさを滲ませながらも、茹でる前段階まで漕ぎつけた事で、一定の達成感を得られた様でした。その後、麺を茹でて無事に完成し食べてみると、一纏めにして捏ねる作業が、如何に蕎麦としてのクオリティを左右するものであるかを実感したのでした。 麺の硬さに違いがあるのは、捏ねている段階で、ある程度想像出来ていたものの、風味や香りの違いも感じる事が出来たのです。風味や香りを左右するのは、粉の割合だけではない事を知り、寮生達は一口一口味わう毎に感じる事の出来る違いを楽しみながら、同時に蕎麦作りの奥深さと、楽しさを知ったのでした。
麺の硬さに違いがあるのは、捏ねている段階で、ある程度想像出来ていたものの、風味や香りの違いも感じる事が出来たのです。風味や香りを左右するのは、粉の割合だけではない事を知り、寮生達は一口一口味わう毎に感じる事の出来る違いを楽しみながら、同時に蕎麦作りの奥深さと、楽しさを知ったのでした。 合の入ったものでした。出汁も昆布からしっかりととり味付けも味見を重ね、思うような味を出すことに成功しました。
合の入ったものでした。出汁も昆布からしっかりととり味付けも味見を重ね、思うような味を出すことに成功しました。